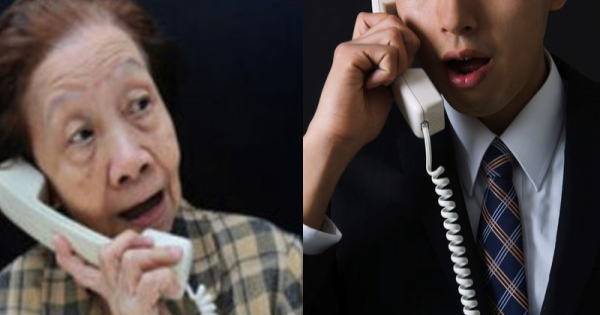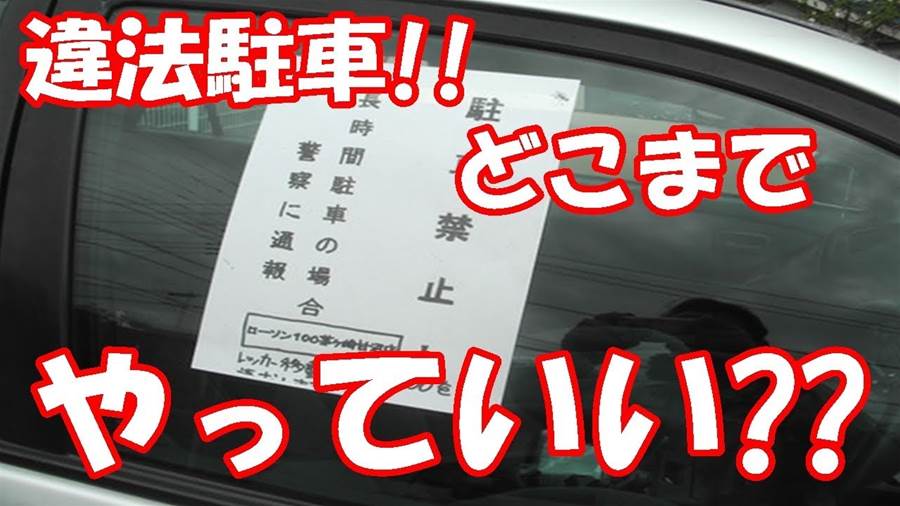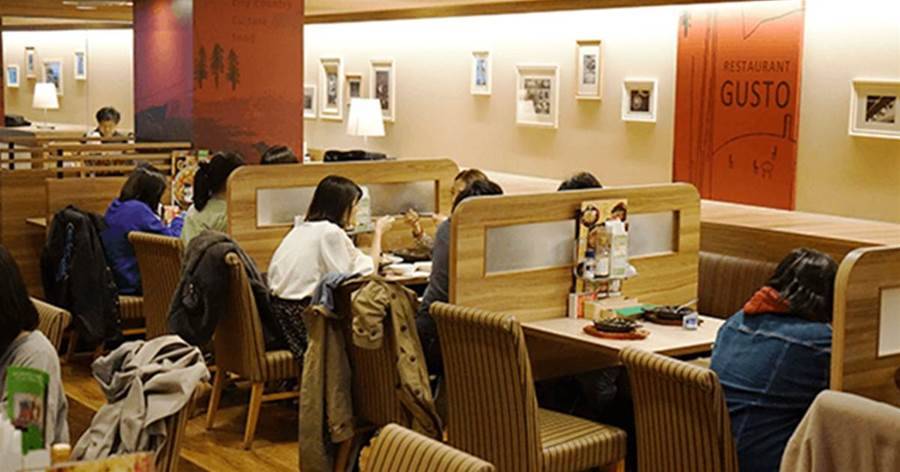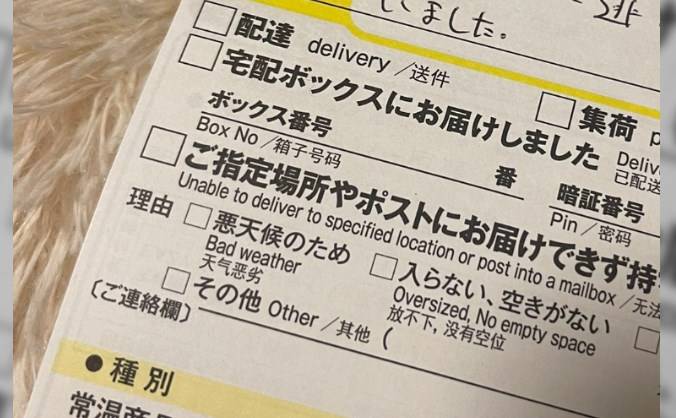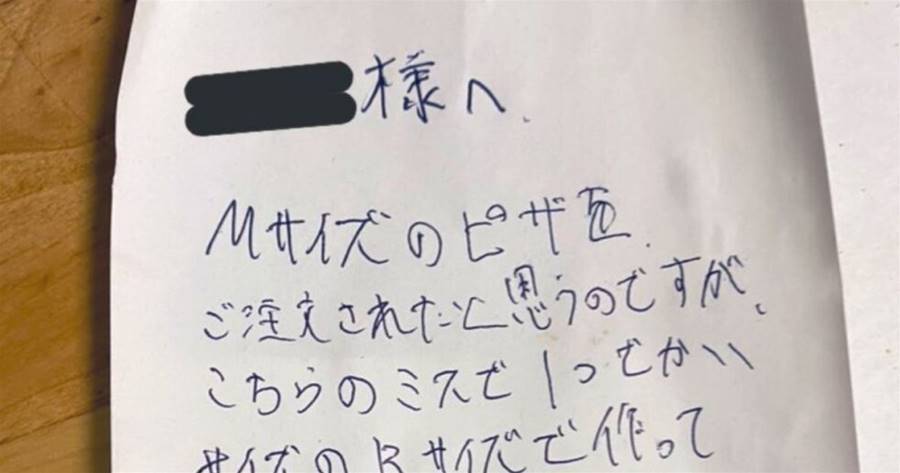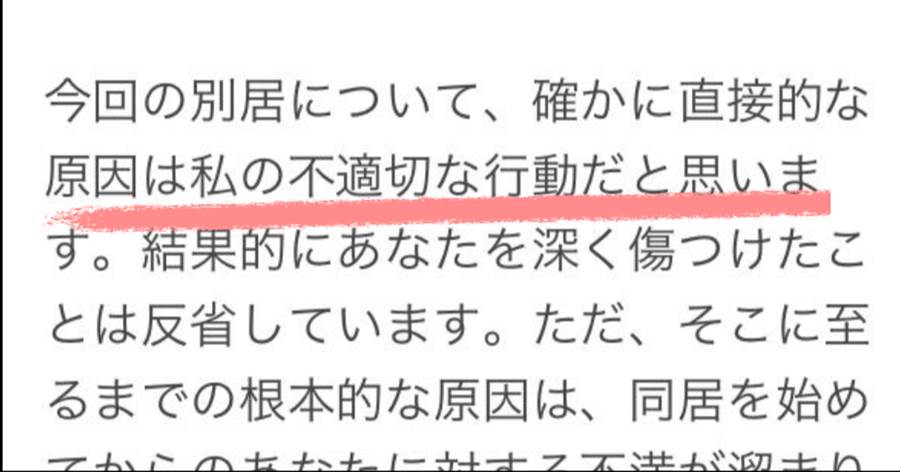ある日の午後、小学生たちが楽しそうにバスの車内を駆け回っていました。その中でも特に元気いっぱいな男の子がいて、彼はふざけて降車ボタンを連打していました。「やっぱ降りませーん(笑)」と大声で叫ぶ彼の姿に、他の乗客たちは笑い声を上げていました。 しかし、このふざけた行為に対して運転手の方は冷静かつ迅速に対応しました。彼は思い切ってバスを停車させ、小学生に厳しく注意をしました。

「降車ボタンは冗談のために使ってはいけません。他の乗客に迷惑をかけることもありますし、私たちの仕事にも支障をきたすことがあります。
「すみませんでした、もう二度としません」と言いながら、彼らは静かに席に戻りました。 この出来事を通じて、小学生たちは大人の立場や他の人への思いやりを学ぶ機会となりました。また、運転手の冷静な対応は乗客たちにとっても心強いものであり、彼らの安全も守られたと感じたのです。 バスの車内でのふざけた行為が、適切な指導と賞賛の声によって改善され、それぞれの役割を果たす大人と子供たちの関係も築かれたのでした。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください